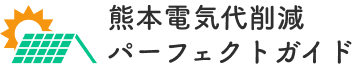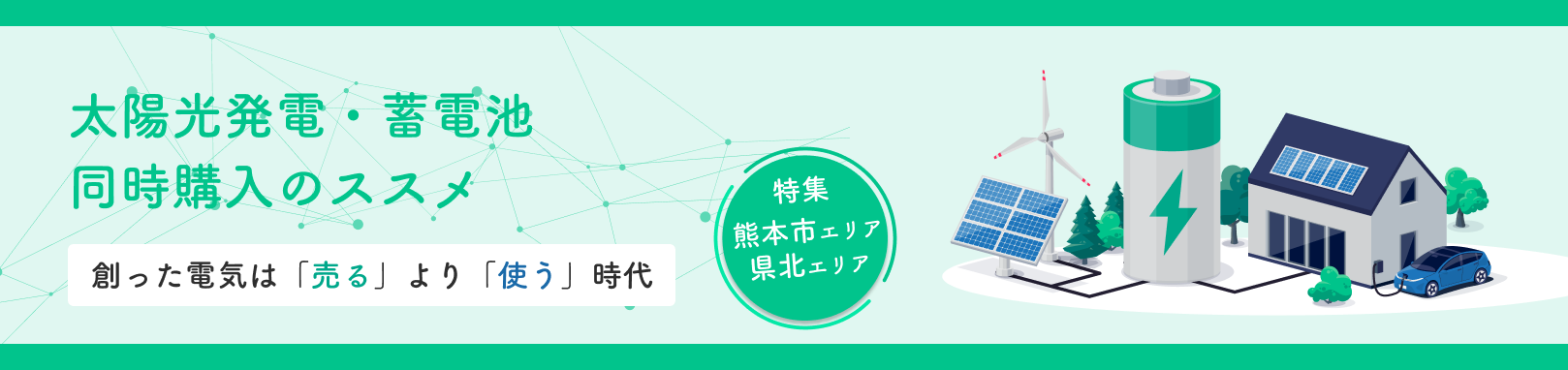近年、農地活用の新たな選択肢として太陽光発電が注目を集めています。特に営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、農業と発電を両立できる画期的な方法として評価されています。
農林水産省の統計によると、2023年度の営農型太陽光発電の設置件数は前年比30%増加しており、今後さらなる普及が期待されています。
また、以下の記事では熊本市で太陽光発電を導入する際のおすすめ会社を紹介していますので、気になる方は参考にしてみるといいでしょう。
農地での太陽光発電の種類と特徴
農地での太陽光発電には、通常の農地転用と営農型太陽光発電の2つの方法があります。
それぞれに特徴があり、状況に応じた選択が必要です。
通常の農地転用による太陽光発電
通常の農地転用は、農地を完全に太陽光発電用地に変更する方法です。農地法に基づく転用許可が必要で、厳格な審査があります。
転用が認められる条件は、第一種農地では原則不可、第二種・第三種農地では一定の条件下で可能です。転用後は農地への再転用が難しいため、慎重な判断が必要です。
また、農業振興地域内の農用地は、原則として転用できません。地域の農業委員会との事前相談が重要で、周辺農地への影響も考慮されます。
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)
営農型太陽光発電は、農地の上部空間に太陽光パネルを設置し、農業と発電を両立させる仕組みです。パネルの下で農作物を栽培しながら、売電収入も得られる画期的なシステムです。
農地転用の許可は一時転用となり、数年ごとの更新が必要です。設置に際しては、遮光率や支柱の配置など、技術的な基準を満たす必要があります。
作物の生育に必要な日照を確保するため、パネルの設置高さや間隔に関する規定も設けられています。
太陽光発電農地転用のメリット
農地での太陽光発電には、以下のような具体的なメリットがあります。
以上のメリットについて詳しく解説します。
農業との両立が可能
営農型太陽光発電では、従来の農業を継続しながら発電事業による収入を得ることができます。パネルの設置高さと間隔を適切に設計することで、作物の生育に必要な日照を確保できます。
実証実験では、一部の作物において収量が従来と同等以上になるケースも報告されています。また、気候変動による異常気象への対策としても有効で、強い日差しや突然の降雨から作物を保護する効果があります。
農業の継続性を保ちながら、安定した副収入を得られる点が大きな特徴です。
固定資産税の節税効果
農地に太陽光発電設備を設置することで、固定資産税の評価額が変更され、一定の節税効果が期待できます。
特に、営農型太陽光発電の場合、農地としての課税評価が維持されるため、通常の転用と比較して税負担を抑えることができます。
また、再生可能エネルギー発電設備に対する税制優遇措置を活用できる可能性もあり、長期的な経営の観点からメリットとなります。
直射日光を遮断する効果がある
パネルによる適度な日陰は、作物の生育にプラスの効果をもたらす場合があります。強い日差しを和らげることで、葉焼けを防ぎ、水分の蒸発を抑制することができます。
特に夏場の高温対策として有効で、作物によってはストレスを軽減し、品質向上につながる可能性があります。また、パネル下の温度変化が緩やかになることで、霜害のリスクも低減できます。
太陽光発電農地転用のデメリット
農地での太陽光発電には、考慮すべき課題やデメリットもあります。導入前に、これらのデメリットを十分に理解することが重要です。
設置する際のコストが高い
営農型太陽光発電の設置費用は、通常の太陽光発電と比べて20-30%程度高くなります。これは、農作業に支障をきたさない支柱の高さ(一般的に3m以上)が必要なため、より強固な基礎工事や資材が必要となるためです。
50kWのシステムの場合、設置費用は2,500-3,000万円程度が目安となります。また、定期的な構造点検や保守管理も必要で、年間の維持費用も考慮する必要があります。初期投資が大きいため、慎重な事業計画が求められます。
農作業機械(トラクター等)の大きさに制限がある
支柱の配置により、大型農業機械の使用が制限される場合があります。特にトラクターやコンバインなどの作業には、支柱間の距離や高さが影響します。
標準的な設計では、支柱間隔を6-8m程度に設定しますが、これにより作業効率が低下したり、使用できる機械が限定されたりする可能性があります。
また、支柱の周りの耕作が難しくなり、実質的な耕作面積が減少することも考慮が必要です。
耕作できる作物が限られる
パネルの影響により、栽培可能な作物が限定されます。一般的に、日照要求量の少ない作物(葉物野菜、イモ類など)が適していますが、コメや果樹など、強い日照を必要とする作物の栽培は難しい場合があります。
また、作物の生育状況によって収量が従来より減少するリスクもあり、栽培品目の選定には慎重な検討が必要です。遮光率によっては、従来の栽培方法の見直しや、新たな栽培技術の習得が必要となることもあります。
実際の費用と収益性
農地での太陽光発電事業を始めるには、様々な費用が必要です。ここでは、具体的な数字を基に収益性を検討します。
転用費用の内訳
農地転用には、申請費用や各種手続きの費用が発生します。標準的な費用の内訳は以下の通りです。
- 農地転用許可申請手数料:4,000円/件
- 土地測量費用:15-20万円
- 土地造成費用:平米あたり3,000-5,000円
- 地質調査費用:30-50万円
- 設計費用:50-100万円
50kW規模のシステムの場合、転用関連の総費用は200-300万円程度となります。また、地域や条件によっては追加の費用が発生する可能性もあります。
設置費用の目安
営農型太陽光発電の設置費用は、規模や設置条件によって大きく異なります。50kWシステムの場合の内訳は以下の通りです。
- 太陽光パネル:800-1,000万円
- パワーコンディショナー:200-300万円
- 架台・支柱:600-800万円
- 工事費用:700-900万円
- 系統連系費用:100-200万円
総額で2,500-3,000万円程度が目安となります。これは通常の太陽光発電と比べて20-30%程度高額となります。
売電収入のシミュレーション
50kWシステムの場合の年間収入例は以下のものです。
- 年間発電量:約54,000kWh
- 売電単価:17円/kWh(2024年度)
- 年間売電収入:約918万円
- 運営維持費:年間100-150万円
- 農地賃借料(該当する場合):年間20-30万円
純利益は年間700-800万円程度となり、初期投資の回収には4-5年程度かかります。ただし、これは理想的な条件での試算であり、実際には気象条件や運営状況により変動します。
熊本県で太陽光発電するならタケモトデンキがおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | タケモトデンキ株式会社 |
| 所在地 | 〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木2丁目11-95 |
| 設立年月日 | 2012年12月 |
| 公式サイト | https://www.takemoto-denki.com/ |
タケモトデンキは、農地における太陽光発電システムの設計・施工においても豊富な実績を持つ専門店です。400件以上の施工実績があり、RECソーラー・ソーラーパートナーズの認定を取得しています。
特に営農型太陽光発電では、農業生産と発電事業の両立を実現する最適な設計を提案します。太陽光発電アドバイザーの資格を持つ竹本社長が、農地の状況や営農計画に合わせた細やかな提案を行います。
また、独自の発電量遠隔監視補助サービスにより、システムの安定運用をサポートします。
まとめ:農地活用の選択肢として
農地での太陽光発電は、農業の継続性を保ちながら安定した収入を得られる有効な選択肢となっています。特に営農型太陽光発電は、農業と発電の両立が可能で、環境への配慮も実現できる新しい農業のカタチといえます。
ただし、導入に際しては以下の点を十分に検討する必要があります。
- 初期投資が通常の太陽光発電より高額
- 栽培可能な作物の選定が重要
- 農作業効率への影響を考慮
- 長期的な維持管理体制の構築
事業計画の策定には、農業経験や地域特性、資金計画など、多角的な視点からの検討が必要です。また、信頼できる施工業者との連携により、長期的な安定運営を実現することが重要です。
農地を活用した太陽光発電は、適切な計画と運営により、農業の新たな可能性を広げる選択肢となるでしょう。